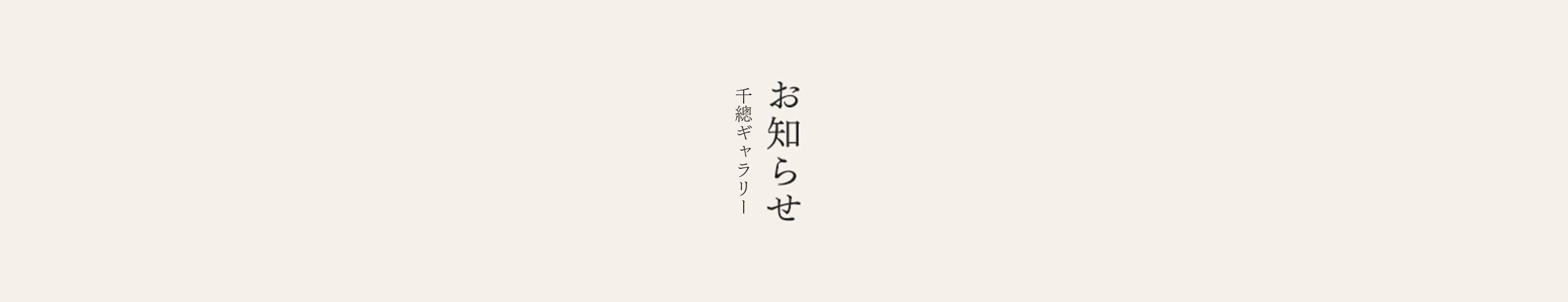COLUMN
2022年02月01日
『景年花鳥画譜』を求めた時代
今回は展覧会関連コラムとして、「花と鳥をうつす」展で展示した『景年花鳥画譜』を切り口に、千總と今尾景年の関わりについてご紹介します。
自然科学にもとづいた写実性

『景年花鳥画譜春の部』明治24年千總蔵
『景年花鳥画譜』は、今尾景年(1845~1924)が原画を手掛けた花鳥画の画譜です。景年は、後に帝室技藝員を務めるなど、京都を代表する日本画家の1人で、花鳥画の名手として知られています。
本書は明治24(1891)年から同25年にかけて、千總の12代当主・西村總左衛門(12代西村)により発行されました。当時は1円60銭で販売されていたようです。
画譜は春・夏・秋・冬の4つの部に分けられており、季節の草花の中で戯れる鳥が、美しい色で刷り出されています。本書の魅力は、なんといっても写実的な鳥や草花の表現でしょう。鳥の表情は愛らしく、飛翔や給餌の仕草も迫真性をもって捉えられています。草木においても、花びらの薄さや葉の硬さなどが、版本を通して伝わってきます。

『景年花鳥画譜夏の部』明治24年千總蔵
こうした表現には、花鳥の名手と言われた景年の技量はもちろんのこと、校訂に関わった博物学者である山本章夫(1827~1903)も重要な役割を果たしたと言われています。
花鳥画の写生画譜は江戸時代にも盛んに制作されていましたが、近代以降は単なる写生ではなく、自然科学に基づく写実性が必要とされました。『景年花鳥画譜』発行の前後にも、博物館や博物学者が関与する 画譜の例が散見されます。
もちろん、事業家である12 代西村も写実性に目を付けていたようです。万国博覧会などを通して海外市場も視野に入れる必要のあった当時において、西洋の自然科学に基づいた表現を目指すことは当然の発想であったのかもしれません。
景年と明治期の千總の「花鳥」
『京都美術雑誌』の2号(明治25年)には、12代西村による『景年花鳥画譜』発売の告知文が掲載されています。告知文によると、12代西村は形式化した図案が使用される現状を憂い、その上で、実物を前にしたかと思うほどに、生き生きとした景年の表現が、染織・陶芸・漆・彫刻などで広く応用されることを期待する旨を述べています。そして、景年の迫真の表現を得るために、鳥や花を収集して景年に提供し写生させたと言うのです。日常で動物園へ通える現代では珍しい話に感じるでしょうか。実は、当時の千總では同様の制作事例が他にも存在します。

〈製品写真〉千總蔵
1900年の第5回パリ万国博覧会に、12代西村が出品した「刺繍額水中群禽図」です。本作では、水辺に戯れる水鳥が緻密な刺繍により表されています。
こうした刺繍作品は、千總の看板商品のひとつとして、国内外で取引されました。
当時の資料によると、本作制作にあたり実際の鳥を飼って刺繍職人の参考とさせたこと、そのために鳥の羽毛の表現が見どころのひとつであったことが記録されています。そして、本作の原画を手掛けたのも、景年でした。本作において、取り寄せた鳥を景年が写生したかは定かではありません。しかし、写実的な景年の花鳥画に近付ける、もしくは花鳥表現にさらなるリアリティを与えるために、鳥は飼育されたのでしょう。本作は、12 代西村に名誉大賞を、景年には協賛銀牌をもたらし、宮内省(当時)に納められました。
こうした作品のように、明治時代の千總における洗練された花鳥表現には、景年が関わっていることが珍しくありません。おそらく、写実性にこだわる 12 代西村の考えを実現できる数少ない画家が、景年だったのでしょう。それは同時に、当時の千總の隆盛にとって、いかに景年が欠くことのできない存在であったかということを示しているのです。
text: 小田桃子(千總文化研究所 研究員)
> 千總文化研究所
「花と鳥をうつす」展