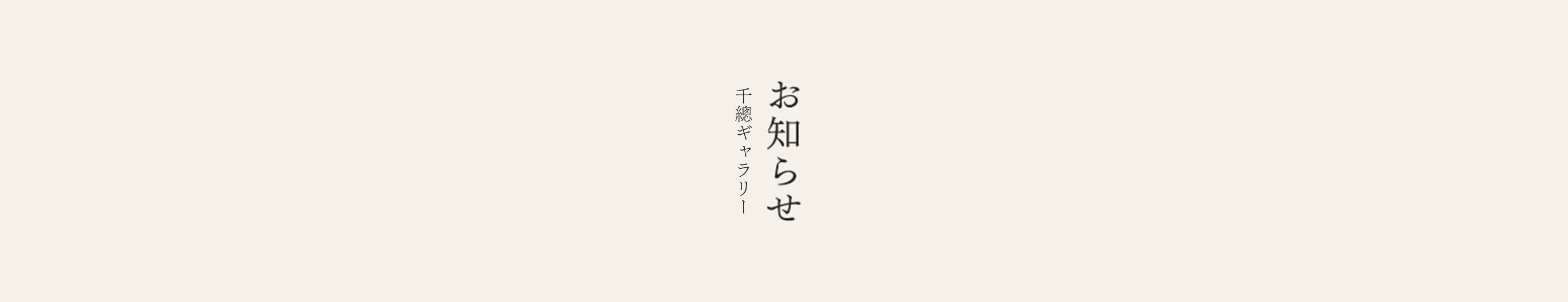COLUMN
2021年09月01日
合成染料が切り拓く新時代
千總ギャラリーで開催している展覧会について、より深くお楽しみいただくために作品を深掘りしたり、会場では触れられていない時代や文化の背景などをご紹介します。
今回は「歩み始めた図案」展で展示している型友禅の作品に関わりの深い合成染料についてご紹介します。
合成染料が切り拓く新時代
友禅染と聞くと、百花斉放と言わんばかりの、豊かで多彩な色を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
現在のように豊富な色数が使用され始めたのは、明治から大正期にかけてと言われています。今回展示している友禅裂でもその一端を垣間見ることができますが、日本画家の繊細な色彩から、百貨店による近代的なファッションのためのビビットな色づかいまで、時代に呼応しながら色が変化しています。
そして、こうした豊かな色彩表現を実現したのが、合成染料でした。

型友禅染裂〈早稲田の薫(かおり)〉
(伝明治38(1901)年製、千總蔵)
大隈重信の温室に咲く色とりどりのコチョウランをモチーフにした
理想の色を求めて—合成染料の開発

型友禅染裂〈薔薇文様〉
(大正8(1919)年製、千總蔵)
合成染料とは一般的に、化学合成により人工的に生成された染料のことを意味します。
1856年にイギリス人、ウィリアム・パーキン(William Perkin)がコールタールからアニリン染料である、紫色のモーブを発明して以来、ヨーロッパでは合成染料の開発が相次ぎました。
合成される染料は主に、自然界では採取が困難、もしくは非常に高価であるものの場合が殆どであり、モーブが開発されるまで紫色には高価な貝紫が用いられていました。
また、同時期の1826年頃には、フランスのジャン・バプティス・ギメ(Jean-Baptiste Guimet)が顔料の合成ウルトラマリンを開発しており、高価な群青やラピスラズリなどの代替品として用いられたと考えられています。
このように19世紀は、化学の力を用いて理想的な色を生み出すことが盛んな時期だったのです。
色鮮やかな型友禅を支えた合成染料
さて、合成染料が、京都へ本格的に輸入され始めたのは明治3(1870)年。京都府は合成染料の産業への導入に取り組み、舎密局などの機関を組織して合成染料の研究を行いました。
そして、その成果の一つともいえるのが、明治14-5年ごろに完成したとされる、縮緬地に写糊(うつしのり)を用いて染める型友禅染、すなわち写し友禅です。写し糊とは、糊に合成染料を混ぜた粘性の高い染料を意味し、写し糊をヘラなどで型紙越しに塗布することで文様を染め出します。

写友禅で用いられるヘラ(一例)
開発者は、一時期は千總でも働いていたとされる広瀬治助(ひろせじすけ)。広瀬は舎密局などで指導を受けて研究を重ね、開発に至りました。開発当初は合成染料の使用などから写し友禅を擬(まがい)友禅と呼ぶなど、懐疑的な見方もありました。
しかし、写し糊が豊かな色彩表現だけでなく作業の効率化も実現したことにより、千總も含め徐々に普及しました。こうした合成染料の研究が、最終的に多くの人々に色鮮やかな衣服を届けることに繋がったのです。
現在では見慣れた色に感じられる色鮮やかな友禅裂は、当時における先端の技術の結晶であり、いつの時代も美しい衣を人々に届けるという、今日までの千總の理念を体現しているとも言えるのではないでしょうか。
text: 小田桃子(千總文化研究所 研究員)
> 千總文化研究所